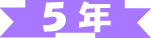 よむ
よむ
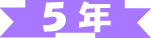 よむ
よむ
| 旅客数と乗り物の利用は どう変わったか |

(1)ねらい
○わが国の「運輸の働き」について,旅客数と交通機関の変化のようすを読みとり,
その原因について考察させる。
○「鉄道と自動車」,「国内航空と国際航空」の現状をデータから把握し,
スピードと運賃との関係を考えさせる。
○この学習を通して,日本地図での地名や交通路,時刻表などの活用を図る。
○この学年の児童にとって,交通機関の進歩発展は興味と関心の最たるものである。
この点を考慮して,学校図書館の資料の集め方,活用に時間を確保したい。
○鉄道の駅と空港との距離,市街地の中心までの時間,フライトの実時間と
時刻表における時間とに差異はあるが,この点の説明は必要であろう。
○新幹線および在来線特急等の利用における時間と料金についてはグラフや表の注を参照。
(3)参考事項
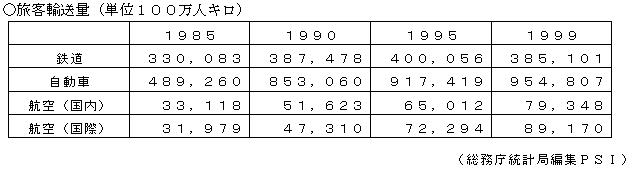 |
 |
○日本地図から次の空港のある場所をさがさせる。
(白地図に位置を記入させる学習も効果的であろう。)
・青森,秋田,旭川,奄美大島,壱岐,石垣,出雲,伊丹(大阪),石見,大分,
大島(伊豆),岡山,隠岐,奥尻,帯広,鹿児島,関西空港,北九州,釧路,熊本,
神津島,高知,小松(金沢),五島福江,佐渡,庄内,仙台,高松,但馬,種子島,
千歳,対馬,徳島,鳥取,富山,長崎,名古屋,那覇,成田,南紀白浜,新潟,新島,
根室中標津,函館,八丈島,八戸(三沢),花巻,羽田,広島,広島西,福岡,福島,
松本,松山,三宅島,宮古,宮崎,女満別,紋別,屋久島,山形,山口宇部,米子,利尻,
礼文,稚内
○輸送の歴史
1872年 新潟-横浜間の鉄道開通
1912年 わが国初のタクシー会社設立
1913年 東海道本線全線複線化
1927年 上野-浅草間に地下鉄開通
1942年 関門海底トンネル開通
1949年 日本国有鉄道発足
1951年 国内民間航空営業開始。羽田-大阪-福岡に一番機飛ぶ(再開)。
ワンマン・バス運転始まる
1952年 日米航空協定成立
1953年 明石-鳴門間初のフェリー運航
1954年 民間航空サンフランシスコ線運航
1956年 東海道本線全線電化完了
1958年 関門海底国道トンネル開通。地下鉄丸の内線開通
1959年 個人タクシー営業許可
1960年 深夜航空便ムーンライト運航
1961年 東京-札幌間初のジェット運航便
1963年 首都高速道路1号線開通
1964年 海外渡航自由化。東海道新幹線東京-新大阪間開通,3時間10分
1969年 東名高速道路全線開通。東名ハイウェイバス開業
1970年 青森-鹿児島間電化ルート完成
1972年 山陽新幹線新大阪-岡山間開通
1975年 山陽新幹線博多まで開通
1976年 新幹線の乗客数10億人突破。宅配事業(宅急便)開業
1977年 国鉄リニアモーターカー初の浮上走行に成功
1978年 青函海底トンネル開通。成田国際空港開港
1979年 国鉄リニアモーターカー試験車が時速504kmの世界新記録達成
1982年 中央高速自動車道全線開通
1983年 中国高速自動車道全線開通
1985年 関越高速自動車道全線開通
1988年 本四架橋瀬戸大橋竣工。北陸高速自動車道全線開通
1994年 関西空港開港
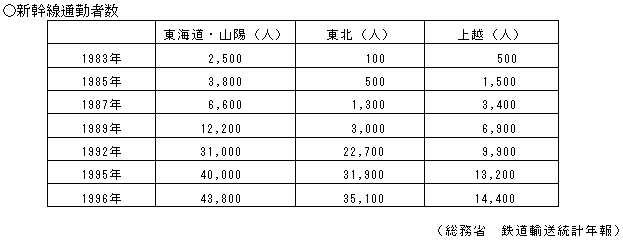 |