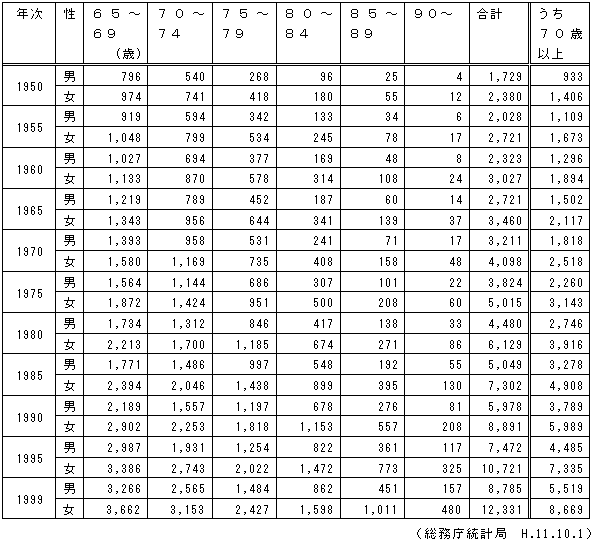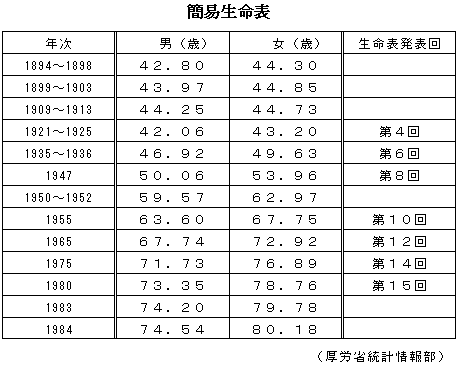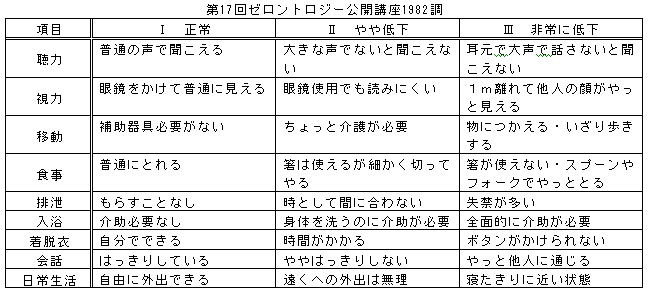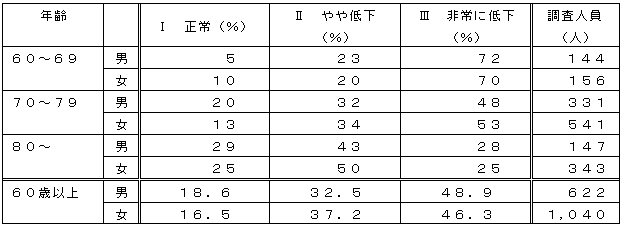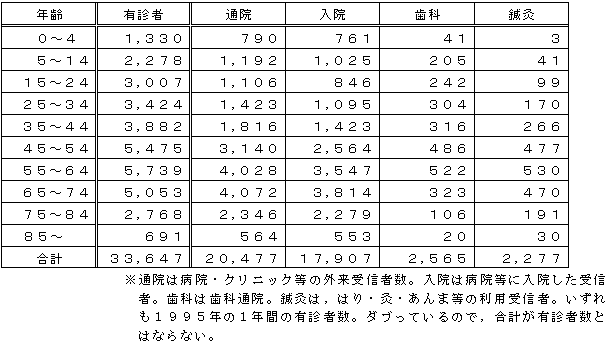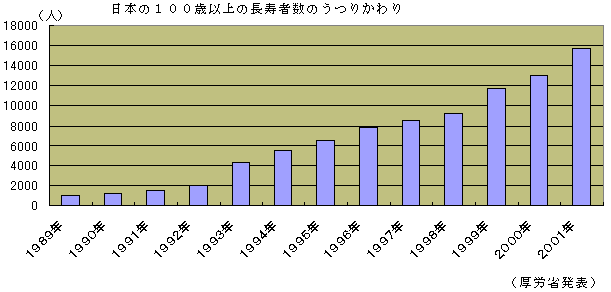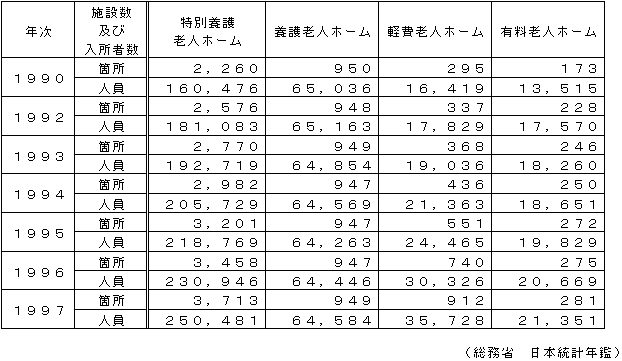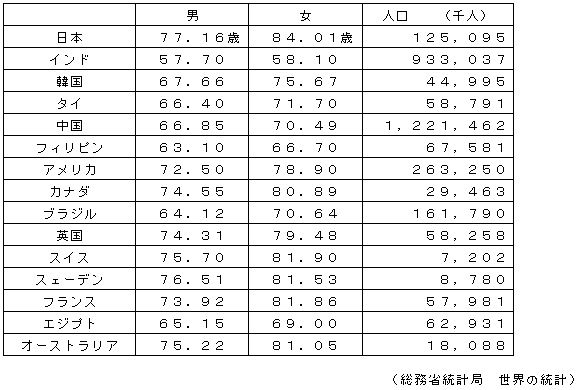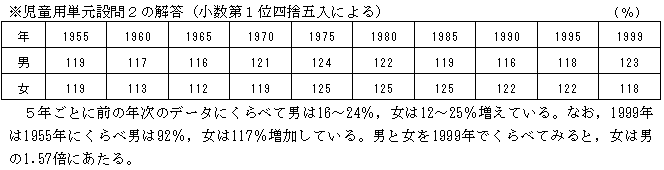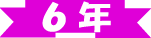 よむ
よむ

(1)ねらい
○日本人の平均寿命の変化は目をみは瞠るものがあるが,
簡易生命表や高齢者人口の増加の資料から一層の認識を深める。
○高齢者は加齢と共に老化することは避けられない。
通院実態や身体的老化度調査の資料から,その内容を読みとり,
高齢者と健康について考える。
○高齢者の意識調査をもとに他の国々(5か国)と
の意識の違いや共通点などを考える。
○この学習を通して,生命がかけがえのないもの,
自他の生命の尊重,父母や祖父母への敬愛,家族の幸せなどを考える。
(2)指導上の留意点
○紙面の都合で多くの資料を提示できないので,
参考事項から必要と思われるものを選択して補充していただきたい。
○平均寿命の飛躍的なのびの基底には生活環境・医療・福祉
・教育・経済・社会参加等が改善されたことがあることを発達段階に即して理解させたい。
○学習指導要領によれば,社会科・総合学習・道徳などで扱う
ことが考えられるが,ここでは道徳の教材として扱ってみた。
従って,生命の尊重や家族の問題,高齢者への思いやりの心
など健康や老化の現実と関連づけて考えさせたい。
(3)参考事項
○「高齢者対策基本法」より。(平成7.11.15)
・我が国は国民のたゆまぬ努力により,
かつてない経済的繁栄を築き上げるとともに,
人類の願望である長寿を享受できる社会を実現しつつある。
今後,長寿をすべての国民が喜びの中で迎え,
高齢者が安心して暮らすことのできる社会の形成が望まれる。
1. 就業及び所得-職業能力の開発,公的年金の適正支給,資産の形成,65歳までの就業の確保
2. 健康及び福祉-保健医療サービス,健康づくり,自然とのふれあい
3. 学習及び社会参加-生涯学習,社会的活動への参加及びボランティア活動
4. 生活環境-自立した日常生活,住宅,交通安全
○年次別・年齢別・性別人口(日本人)
○日本人男女の平均寿命の推移
○老化のパラメーター(日常活動指数ADLの判定基準)東京都老人総合研究所
○年齢階級・通院状況有診者数(1995年) (単位千人)
○全国高齢者名簿(長寿番付)について
100歳以上の長寿者は1990年代から急速に増え始め,わずか5年で2倍になった。
「長寿番付」は毎年9月30日までに100歳以上となるお年寄りを9月1日現在で集計している。
2001年は15,475人(男2,541人,女12,934人)で,2000年に比べ2439人増え過去最高を更新した。
女性の占める割合は83.6%に達した。長寿者は統計をとり始めた1963年は153人で,2001年で
100倍を超した。10年前の1991年は3625人(男749人,女2,876人)だったが,5年前の1996年は
7,373人(男1,400人,女5,973人)で,年を追うごとに日本の高齢化の様子がグラフによく
表れている。人口10万人あたりの長寿者を都道府県別にみると,最も多かったのは沖縄県,
次いで島根,高知,熊本,鹿児島の各県で,逆に少ないのは埼玉県,以下,愛知,青森,茨城,
千葉の各県の順だった。日本一の長寿は鹿児島市在住の女性本郷かまとさん,
2001年9月16日現在で114歳になる。男性では福岡県小郡市在住の中願寺雄吉さんで112歳である。
(朝日新聞掲載記事)
○主な老人福祉施設と入所者数
○平均余命の国際比較(1986~2000年)
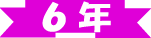 よむ
よむ
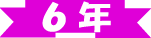 よむ
よむ