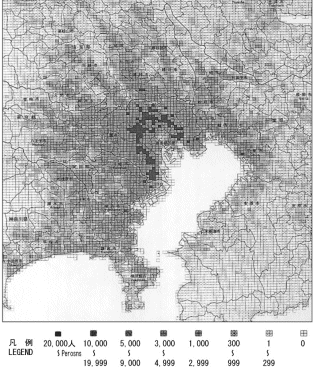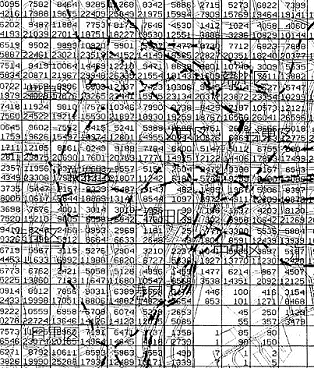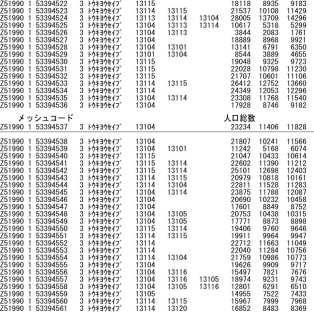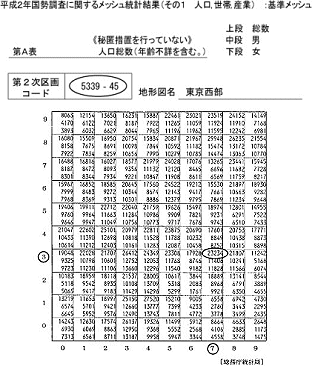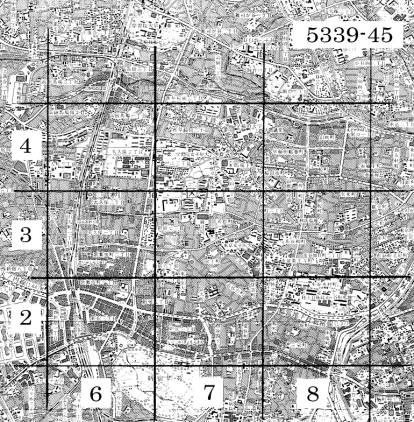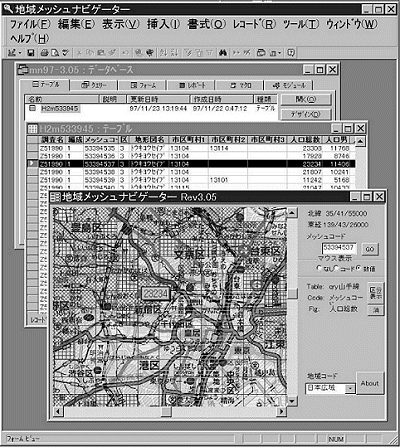- ESTRELA 1998年1月号掲載
- 総務庁統計局統計情報課
- 地域総合統計係長
- 槙田 直木(Makita Naoki)
- 本稿では、地域メッシュ統計のデータを市販の電子地図上に簡便に表示するシステム「地域メッシュナビゲーター97 for ProAtlas97+Access97」(参考[1]。以下、「メッシュナビ」と言う。)について2回にわたり紹介する。メッシュナビは、筆者が休日に自宅のパソコンにて開発したものであり、電子地図とデータベースソフトの比較的安価な組み合わせの上で稼動する。
前編では地域メッシュ統計のデータ利用に当たって生じる「課題」とそれを解決するためのメッシュナビ及びその仕組みを、後編ではメッシュナビの具体的な使用方法及び利用例を説明する。
- 1.地域メッシュ統計とメッシュナビ
- (1)便利な! 地域メッシュ統計
- 地域メッシュ統計は、人口や事業所数等を地域メッシュという小地域区画ごとに表章するものであり、地図の上でそれを視覚化したものは大変便利なものである。例えば、国会等移転審議会の場においても地域メッシュ統計は用いられており、地域開発や防災・環境計画、商圏分析等官民を問わず多方面において利用されている(参考[2])。
- その特徴としては次のようなものがある。
- 単位となる区画は分析に適当な広さ(総務庁統計局の地域メッシュ統計は、基準メッシュ(約1km四方。3次メッシュとも言う)ごとに編成されている。さらに人口集中地区については4次メッシュ(約500m四方)ごとにも編成)。
- 全国についてほぼ一定の形状により地域比較することが可能。
- 時系列比較も可能(地域メッシュ区画は、行政界とは別に緯度経度により設けられているため、市区町村の廃置分合の影響は受けることはない)。
- 地域メッシュ統計は、以下の媒体により提供されている。
- 地域メッシュ統計地図 階級メッシュ・マップ(図1)
- 地域メッシュ統計地図 デジタルメッシュ・マップ(図2)
- 磁気ファイルデータ(図3)
- 結果表出力プリント(図4)
-
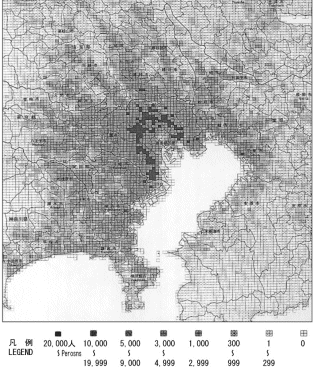 |
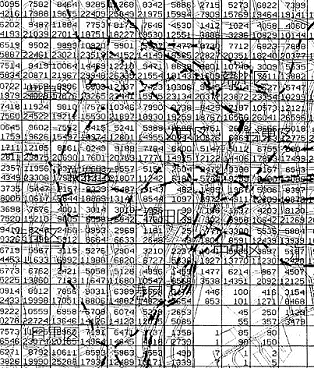 |
| 図1 |
|
地域メッシュ統計図 階級メッシュ・マップ
(その1 人口、世帯、産業)首都圏
(総務庁統計局) |
|
| 図2 |
|
地域メッシュ統計地図 デジタルメッシュ・マップ
(東日本編)5339東京(部分)(総務庁統計局) |
|
-
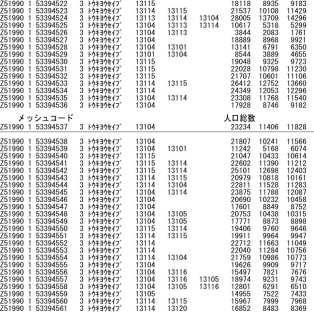 |
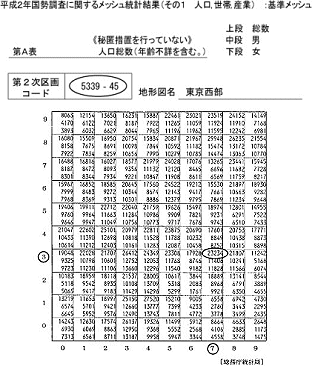 |
| 図3 |
|
磁気データファイル(一部加工)
(総務庁統計局) |
|
| 図4 |
|
結果表出力プリント(一部加工)
(総務庁統計局) |
|
-
| 図1〜4は、いずれも平成2年国勢調査に関する地域メッシュ統計によるもの。図2〜4では、総務庁統計局のある地域メッシュ(地域メッシュ・コード5339-45-37)に、○や下線で印を付している。 |
- 例えば、1.階級メッシュ・マップを眺めると、人口の分布を地図の上で視覚的に把握することができる。
- (2)敷居の高い? 地域メッシュ統計
- しかし、本格的な分析をしようとすると、市販の地理情報システム(GIS)ソフトを駆使して3.磁気ファイルデータを料理する必要がある。このGISソフトは、実際のところ高価なものが多く、さらに背景地図(地域メッシュ区画のバックグラウンドに配する地理情報)を別途用意しなければならないことも多い。お金も技術もあまりない素人にとっては、地域メッシュ統計のデータを扱うことはあまり容易ではないものになっている。
- 地域メッシュ統計のデータは、「地域メッシュ・コード」と「統計値」の対により定義されるものである。この地域メッシュ・コードが少々曲者である。地域メッシュ・コードと地域メッシュ区画(地図上の位置)との相互の対応をつけるには、ちょっとした手間がかかる。
- 例えば、総務庁統計局の所在地は地域メッシュ・コード5339-45-37に対応するという事実を検証してみよう。
- 地域メッシュ・コードは、まず定義に従ってそれを緯度経度に変換し※(これは今の時代コンピュータに任せれば済むことである)、その上でその緯度経度がどの地域を指すか地図を参照しなければならない(これが大変)。
-
| ※メッシュ・コード |
: |
53 |
39 |
4 |
|
5 |
3 |
|
7 |
|
|
|
| 区画南西点の北緯 |
: |
(53 |
|
+4 |
÷8 |
|
+3 |
÷80) |
|
×2/3 |
= |
35度41分30秒 |
| 区画南西点の東経 |
: |
100 |
+39 |
|
|
+5 |
÷8 |
|
+7 |
÷80 |
= |
139度42分45秒 |
| → 対応する3次メッシュ区画 北緯: 35度41分30秒〜42分0秒 |
| (南北方向30秒×東西方向45秒) 東経:139度42分45秒〜43分30秒 |
| メッシュ・コードの組立の詳細については、地域メッシュ統計のホームページ(参照[3])を参照。 |
|
- メッシュ区画を特定する方法として、国土地理院の1:25000地形図(以下、「地形図」という)(図5)を用いるものがある。地形図の右上肩には6桁の2次メッシュ・コードがあらかじめ印刷されているので、あとはその地形図の中で残り2桁の3次メッシュ区画を特定すればよい。そのためには、地形図の図郭をその上辺と下辺、左辺と右辺に描かれている9つの小さなマークを結ぶようにメッシュ線を引くことにより10×10の3次メッシュ区画に仕切り、縦軸、横軸の順にます目の数を読み取ればよい。
-
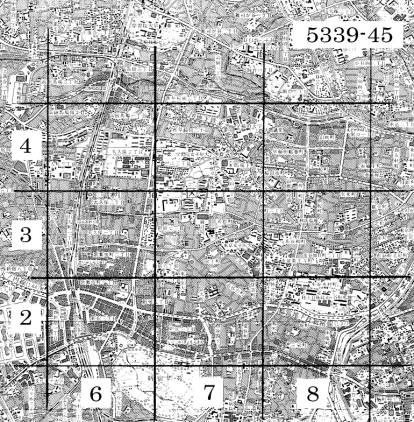 |
| 図5 1:25000地形図 東京西部(部分)(国土地理院)
|
- これが典型的なメッシュ区画の特定方法であるが、実際にそれを日本全国くまなく行うためには延べ4,376枚の地形図を揃えた上でメッシュ線引きをしなければならず、現実にはかなりの資源(費用・労力)を要することになる。
- (3)地域メッシュ統計を手軽に扱うメッシュナビ
- そこで筆者は上記(2)の「敷居」を低くするために、電子地図を用いてナビゲーター(図6)を開発した。メッシュナビにより、地図にマウスをかざすだけでメッシュ・コードを表示させたり、与えられた地域メッシュ統計のデータ(メッシュ・コード+統計数値)を基に階級別塗り分け地図を作ることができる。
- このプログラムを利用するには、2つのアプリケーション(電子地図ProAtlas97及びデータベースソフトAccess97)を利用者側において用意する必要があるものの、それでもメッシュナビは既存のGISソフトを使う方法に比べて安価なソリューションを提供するものとなっている。
-
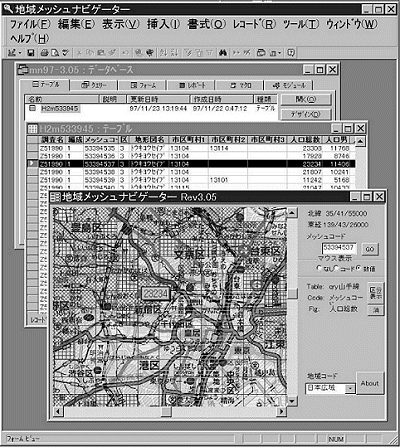 |
| 図6 地域メッシュナビゲーター(地図上の文字ラベルは総務庁統計局の位置の人口総数を表示している。) |
- 2.メッシュナビの下敷きとして用いるアプリケーション
- (1)安くかつ高度化した電子地図
- 電子地図はパソコンソフトの一ジャンルとして従来から存在していたものの、正直なところ筆者は、「電源を入れる」ことなく手元でパッとめくっていける地図帳の気軽さの方に好感を持っていた。ところが、近頃の電子地図は、「地図をプログラミングする」という付加価値を獲得したことにより、がぜん便利で面白いものになってきた。その一つが筆者がメッシュナビにおいて下敷きにしているProAtlas97(参考[4])である。
- ProAtlas97におけるその「プログラム」の機能とは、次のようなものがある。
- 地図の画面表示
- 地図階層(縮尺)の切り替え
- 緯度経度を基にした地図面の移動
- 緯度経度を指定して地図面を移動させることが可能
- 地図上への文字表示
- マウス位置の緯度経度の収得
- これらは、Windows環境において一般的に利用可能なActive Xコントロールによるオートメーション機能(後述)により提供されるものである。
- これにより、自分の意のままに地図を操り表示させることができる。
- ProAtlas97には、地域を都市部に絞り込んだ「首都圏」、「中部」及び「近畿」と、全国をくまなくカバーする「日本広域」の4つのシリーズがある(平成9年11月現在)。
- 筆者が開発したメッシュナビは、ProAtlas 97の4シリーズのいずれにも対応させて作成しており、「日本広域」を使えば北は北海道、南は九州、沖縄まで、地域を問わず、地域メッシュ統計のデータを表示させることができる。
- ProAtlas97について付け加えるならば、この電子地図の画像は、開発元のアルプス社が刊行する地図帳に用いるために初めからコンピュータの上で描かれたものであり、線と面により構成された(表現力の貧弱な)地図の画像に比べて、見やすくきれいなものになっている。また、実売価格も5,000円前後と比較的安価であり、筆者は個人的に気に入っている。
- (2)プログラミング環境としてのデータベースソフト
- パソコンユーザーにとって表計算ソフトはもうおなじみであろうが、データベースソフトを使ったことがあるという人はさほど多くはないであろう。
- データベースソフトの基本的な考え方は、次の機能で構成されるものである。
- テーブル
- データを格納する入れもの。「レコード」と呼ばれる行を単位として一本のデータが格納される。
- メッシュナビでは、地域メッシュ統計のデータをテーブルとして取り込ませる。
- クエリー
- テーブルを加工するもの。指定した条件によりテーブルからレコードを抽出したり、新規のテーブルを作ったりすることができる。
- 地域メッシュ統計データの対象地域はクエリーで絞り込むと便利である。
- フォーム
- データベースソフトの操作画面(インターフェイス)を定義・表示するためのもの。
- (図6参照。ウィンドウの中にある3つの子ウィンドウのうち、真中が1.テーブル、下が3.フォームである。)
- メッシュナビは、3.フォームに電子地図を「埋め込む」ことにより実現するものである。
- ここでの「埋め込む」とは、前述のActive X(以前のOLE=Object Linking and Embedding)コントロールによるオートメーション機能のことであり、簡単に言うとアプリケーションが他のアプリケーションの要素を「部品」(オブジェクト)として操作できることである。
- メッシュナビを開発するに当たって、筆者が用いたデータベースソフトは、プログラミング環境を持ったAccess 97(参考[5])である。「部品を操作する」ためにはプログラミング言語として、Visual Basic、C++やDelphi等を習得する必要がある。しかし、そのような専門の開発言語を購入しなくても、普段使っているアプリケーションにオマケで含まれているプログラミング環境により、ある程度複雑な処理をさせることができる。特にExcelやAccessは、機能は制限されているものの内部的にVisual Basicを持ち合わせている。
- 電子地図をデータベースソフトに埋め込むというアイディアにより、次のようなことを実現することができる。
- 3.フォームに埋め込んだ電子地図の上にかざしたマウスの座標をプログラムに読み取らせ、その位置のメッシュ・コードを計算・表示させる。
- データベースが持つ地域メッシュ統計のデータ(1.テーブル又は2.クエリー)をプログラムに読み取らせ、メッシュ・コードに対応する緯度経度の区画を計算し、3.フォームに埋め込んだ電子地図の上で該当する位置に統計値を表示させたり、塗り分け地図を描いたりする。
- メッシュナビは、このような仕組みで動いているのである。
- *参考
- [1] 地域メッシュナビゲーター97 for ProAtlas 97 + Access 97:
- URL:/freesoft/meshnavi/index.html
- なお、メッシュナビの開発に当たり、次の記事が刺激となった。古田裕繁著『サンデー・プログラマーのGISへの挑戦』(1997年1月〜本誌連載)
- [2] 第3回国会等移転審議会調査部会議事要旨:
- URL:http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/daishu/council/c_04/iten03.html
- 他に、川崎茂著『国勢調査のメッシュ統計』(1995年9月本誌)、松井信夫著『地域メッシュ統計の利用が多い理由』(1996年10月日本統計協会「統計」)等を参照。
- [3] 総務省統計局地域メッシュ統計のホームページ:
- URL:http://wwww.stat.go.jp/05g.htm
- [4] ProAtlas 97:アルプス社ホームページ
- URL:http://www.alpsmap.co.jp
- [5] Access 97: マイクロソフト社ホームページ
- URL:http://www.microsoft.com/japan
Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.
|