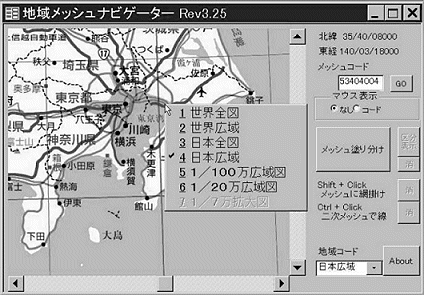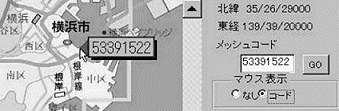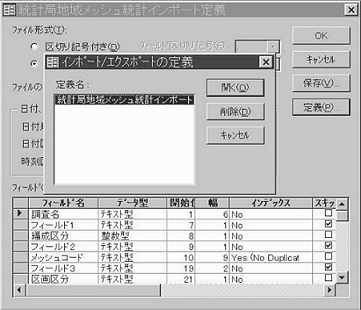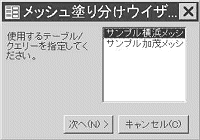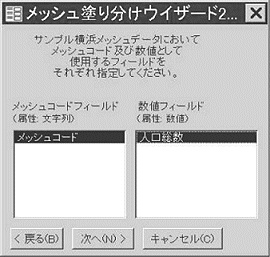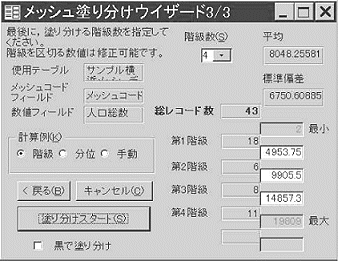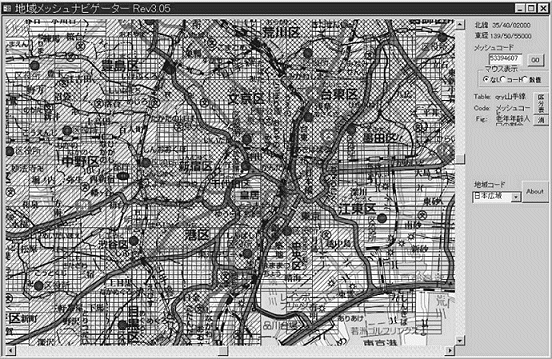- ESTRELA 1998年2月号掲載
- 総務庁統計局統計情報課
- 地域総合統計係長
- 槙田 直木(Makita Naoki)
- 前編に引き続き、地域メッシュ統計のデータを電子地図上に簡便に表示するシステム「地域メッシュナビゲーター」(参考[1])(以下、「メッシュナビ」と言う。)について紹介する。前編では、
- 1.地域メッシュ統計とメッシュナビ
- 2.メッシュナビの下敷きとして用いるアプリケーション
- として、地域メッシュ統計のデータ利用に当たって生じる「課題」とそれを解決するためのメッシュナビのしくみを説明した。
- 後編では、メッシュナビの具体的な機能及び利用例等について解説する。
- 3.メッシュナビの機能
- (1)動作環境
- 比較的安価な電子地図及びデータベースソフトの組み合わせの上で稼動するメッシュナビ(ファイル名mn97.mde)は、メッシュナビのWebサイト(参考[1])からダウンロードできる。
- メッシュナビは、次の2つのアプリケーションが導入済みのWindows95/WindowsNT環境下で稼動する。
- アルプス社ProAtlas97(参考[2])(首都圏、中部、近畿及び日本広域に対応。なお、ProAtlas 97 DVDについては対応未定
- Microsoft社Access97(参考[3])
- mn97.mdeは、Access97の上で起動する。起動すると、左側に地図面、右側に情報面が並んだメッシュナビフォームが自動的に立ち上がる(図1)。
- 地図面はProAtlas97そのものであり、Pro Atlas97本体と同様に、地域を選択したり、移動や縮尺変更したりすることができる。表示している地図を移動させるにはマウスを地図面に置いて左クリックボタンを押しながら動かせばよい(地図を「握って引っ張る」感覚)。また、マウスを地図面において右クリックすると、その位置において表示可能な縮尺のリストが現れる(図1)。
-
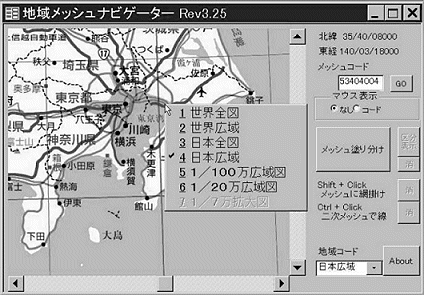 |
| 図1 |
|
地域メッシュナビゲーター
マウス位置において表示可能な縮尺のリストを表したところ。 |
|
- (2)任意地点のメッシュコードを表示
- 地図面にマウスをかざすと、それに連動して情報面に緯度・経度(北緯と東経)及びメッシュコードが表示される。表示される緯度経度に関して、筆者はProAtlas97「首都圏」を用いて新宿区及び横浜市について精度を検証したが、国土地理院の1:25000地形図の緯度経度との誤差は認められず、メッシュコードについても正確に表示されていることが確認できた。
- なお、メッシュナビでは、次のような機能も併せ持っている。
- 「メッシュコード」欄(テキストボックス)に8桁の基準メッシュコードを入力して「GO」ボタンを押すと、地図面がその位置に移動する。
- 「マウス表示」オプショングループにおいて「コード」ラジオボタンを選択した状態で地図面にマウスをかざすと、当該位置におけるメッシュコードを示したテキストラベルがマウスの先端位置に表示(図2)。
- キーボードのShiftキーを押しながらマウスの左ボタンをクリックすると、当該メッシュ区画に網かけを行う。
- キーボードのCtrlキーを押しながらマウスの左ボタンをクリックすると、当該メッシュを含む2次メッシュ区画について地域メッシュ線を引く。
ただし、この機能は、ProAtlas97自身の線画機能の実装が不完全であるため、表示している地図面が小縮尺の場合、地域メッシュ線が欠けてしまう障害がある。
-
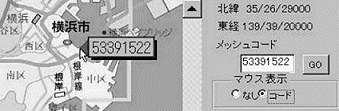 |
| 図2 |
|
マウス表示を「コード」にすると、
マウスの先端位置のメッシュコードが表示される。 |
|
- (3)地域メッシュ統計データの取り込み
- メッシュナビには、地域メッシュ統計データに応じて地域メッシュ区画を塗り分ける機能がある((4)にて後述)。この機能を引き出すために、ユーザーは事前にメッシュデータをAccessのテーブルとして取り込む(インポートする)必要がある。
- 地域メッシュ統計の磁気データファイルは、固定長形式ファイルとして提供されている(前編の図3)。一般に固定長形式を扱うには、まず磁気データファイル編成仕様書に記載されているデータレイアウトフォームを参照し「○桁目から△桁目までがメッシュコードであり、その属性は文字列として‥‥」と、データ構造を一つ一つ定義する必要がある。
- そこでメッシュナビは、その作業を簡略化するために、総務庁統計局の地域メッシュ統計データ(平成2年国勢調査、平成3年事業所統計調査及び平成2・3年リンクのもの)の様式に沿って固定長形式ファイルを読み込むための「インポート/エクスポートの定義」を組み込んでいる(図3−1、2)。この定義ではメッシュコードの桁などの基本的な情報をmn97.mdeが持っており、ユーザーがすべきことは必要な項目(「人口総数」、「従業者数」等)の桁を特定するだけで済む。なお、メッシュナビの内部処理における制約のため、テーブル/クエリー名には半角空白文字を含ませてはならない。
- Access97には、テーブルのフィールド数は最大255という制限事項があり、地域メッシュ統計の磁気データファイルにある全ての項目を1つのテーブルに取り込ませることはできない。しかし、たいていの用はこの制限の中で済ますことができるであろう。
-
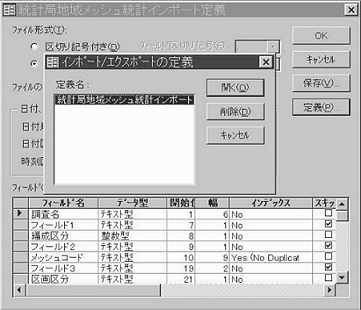 |
 |
| 図3-1 |
|
「インポート/エクスポートの定義」として
「統計局地域メッシュ統計インポート」を選択する。 |
|
| 図3-2 |
|
固定長形式ファイルが所定の区切りで取り込まれる。 |
|
- (4)メッシュデータを基に地図を塗り分け
- いよいよ、メッシュナビ最大の特徴である塗り分け機能について説明する。これは、順に問いに答えるだけで、任意のメッシュデータ(約1km四方の基準メッシュ)を基に電子地図の上で階級メッシュマップを作るというものである。「メッシュ塗り分け」ボタンを押すと3段階からなる「メッシュ塗り分けウィザード」が展開する。
- 使用するメッシュデータの入ったテーブル/クエリーを指定する(図4−1)
データベースファイルであるmn97.mdeが持つテーブル/クエリーの一覧が表示されるので、そこから使用するものを選択する。
(クエリーは、テーブルにあるメッシュデータの範囲を絞り込む際に使うと、便利である。)
- 使用するメッシュコード及び数値が入ったフィールドを指定する(図4−2)
1.で指定したテーブル/クエリーが持つフィールドが表示されるので、そこからメッシュコード及び数値として使用するフィールドを選択する。
ここで、メッシュコードとして指定するフィールドは「重複なしインデックス化されたテキスト型」、数値として指定するフィールドは「数値型」としておく必要がある。ただし、メッシュナビの「インポート/エクスポートの定義」を使ってデータをインポートすれば、これら条件を満たすような属性にしてデータは取り込まれているので、このような注意を気にする必要はない。
- 階級分けを指定する(図4−3)
メッシュ塗り分け地図において適用する階級分けをここで定義する。ユーザーは、階級(等間隔)、分位(等度数)又は手動(任意の間隔)により階級分けを設定することができる。また、階級数についても1から5までの間でユーザーが選ぶことできる。
-
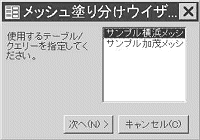 |
| 図4-1 |
|
使用するメッシュデータの入った
テーブル/クエリーを指定。 |
|
-
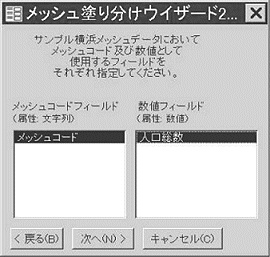 |
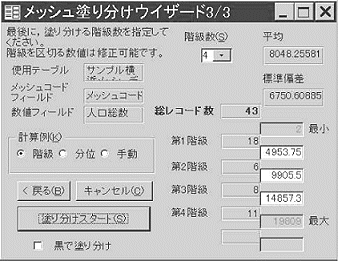 |
| 図4-2 |
|
使用するメッシュコード及び
数値が入ったフィールドを指定する。 |
|
|
- 以上の3段階を踏むと、図5のような塗り分け地図を手に入れることができる。この塗り分け地図は、「区分表」ボタンを押すことにより「3.階級分けを指定する」のダイアログを呼び出して、階級の設定をやり直すことができる。また、「マウス表示」オプショングループの「数値」ボタンを選択して塗り分け地図にマウスをかざすと、当該メッシュにおけるメッシュデータ値を示したテキストラベルがマウスの先端位置に表示されるようになる(前編の図6)。
-
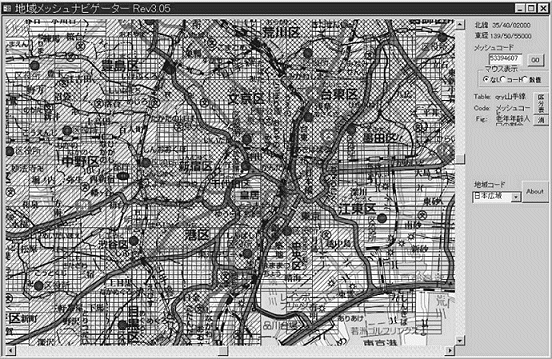 |
| 図5 |
|
老年人口の割合 東京 山手線周辺(平成2年国勢調査に関する地域メッシュ統計 |
|
- 4.メッシュナビによる塗り分け地図の利用例
- (1)描画例
- 図5は、メッシュナビの塗り分け機能により、東京の山手線周辺の老年人口の割合を描いたものである(平成2年国勢調査に関する地域メッシュ統計による)。
- この図では、山手線の東側半分は西側半分に比べて網かけが濃く施されており、いわゆる下町地域において高齢化の進んだメッシュが多くなっていることが見てとれる。
- (2)塗り分け地図のプリント
- 地域メッシュ統計データを基に作成した塗り分け地図をプリンターに出力するためには、ユーザーはモニタのイメージをいったん画像処理ソフトに取り込んで、そのソフトからプリントすることにより行わねばならない。
- 具体的には、モニタに塗り分け地図を表示させた状態でキーボードのPrintScreenキーを押し(これによりモニタ全体がクリップボードにコピーされる)、Windows標準アクセサリである「ペイント」などにおいてそのイメージを貼り付けて加工、印刷すればよい。
- 5.メッシュナビの限界と課題
- 以上で紹介したメッシュナビは、本格的なアプリケーションとしては物足りなさを覚えることが多いかもしれない。例えば、メッシュナビでは塗り分け地図の網かけの種類や色があらかじめ固定されており、ユーザーの好みに応じた独自の設定はできない。また、塗り分け地図のプリントは、メッシュナビ単体では不可能となっている。
- これらのことは、限定されたプログラミング環境であるAccess97ではなく、本格的なVisual Basicを用いてメッシュナビを開発すれば、部分的には解決可能であろう。しかし、電子地図であるProAtlas97自身も部品としての機能が現状では貧弱であるため(例えば、線画・網かけ機能)メッシュナビを完璧な「作品」として仕上げることはできないと筆者は考えている。
- そもそもメッシュナビは、本格的なプログラミング専用ソフトや技術書を購入することなく、筆者が休日の暇に任せて自宅のパソコンを使って趣味で作り始めたものに過ぎず、地域メッシュ統計データをお手軽に表示できればそれでよしとしている。現状のメッシュナビを越える機能を求める向きの方には、市販の地理情報システム(GIS)ソフトを利用することをお薦めする。
- それでも、メッシュナビは以下のような将来構想を暖めている。
- 塗り分け地図作成時に凡例表示(補記)
- 地域メッシュ統計データを取り込んだレコード形式(1行の文字列が1メッシュを表す)のテーブルから、マトリックス形式(マス目状にメッシュデータ値を配置して表す)のテーブルを生成(補記)
- これらについてはメッシュナビ・ユーザーからの意見や感想を踏まえつつ、追々対応していきたいと考えている。
- 総務庁統計局では、今春、平成7年国勢調査に関する地域メッシュ統計について磁気データのファイル提供を開始する予定である。このメッシュナビが、地域メッシュ統計の利用、理解の助けになれば幸いである。
- *参考
- [1] 地域メッシュナビゲーター97 for ProAtlas 97 + Access 97:
- URL:/freesoft/meshnavi/index.html
- なお、メッシュナビの開発に当たり、次の記事が刺激となった。古田裕繁著『サンデー・プログラマーのGISへの挑戦』(1997年1月〜本誌連載)
- [2] ProAtlas 97:アルプス社ホームページ
- URL:http://www.alpsmap.co.jp
- [3] Access 97: マイクロソフト社ホームページ
- URL:http://www.microsoft.com/japan
- *補記
-
Copyright (C) 1996 Sinfonica All Rights Reserved.
|